掲載・引用:
前回、日米間の属国協定の最たるものである「日米地位協定」について真実を暴露した、前泊博盛氏の本を書評した。「日本国内にアメリカが欲しいだけの基地を確保する」というのが日米安保体制の本質であった。その維持のために、アメリカは地位協定(かつての日米行政協定)というものを日本側に強制的に結ばせた。
それでは、日米同盟体制を維持するために存在する協定はこれだけなのか。実は、もう一つ、日米原子力協定(1988年)というものがある。この協定は日本では中曽根政権時代の1980年代に改定交渉が行われたものである。この協定は発効した1988年の30年後の2018年まで有効である。
結論から言えば、この改定原子力協定こそが、日本の核武装を不可能にしながら、同時に日米同盟体制の重要な枠組みとして日本の原子力政策を縛り付けてきた諸悪の根源である。日本の原子力発電所は、日本の核武装を目論んだ正力松太郎の重要な政治戦略として生まれたが、この正力の自立路線が中曽根康弘に代表される、アメリカの属国路線に取って代わった段階で、日米原子力協定を出発点にする日本の原子力政策は、上から大きくアメリカにコントロールされていくことになったのである。
私は、そのことを原子力協定の全文を詳しく精読していき、さらに最近発売された、苫米地英人(とまべちひでと)氏の『原発洗脳:アメリカに支配される日本の原子力』(日本文芸社)と、有馬哲夫『原発と原爆』(文春新書)などを読み解いていくうちに発見した。この改定協定をめぐっては、日本の原子力外務官僚の中で、「初めて日米が対等に渡り合った交渉」(外務官僚の遠藤哲也の言)というような、「神話」が流布されてきた。私はここでこの神話を叩き壊さなければならない。
結論から言えば、私は、日本の個別の原子力発電の再稼働問題と、日本の核武装戦略から出発した六ケ所村の日本原燃が運営する再処理工場の稼働問題は大きく分離して、政策的に議論が行われるべきである。そして、再処理工場を動かさないという政策大転換をしたうえで、他の原子力発電所の稼働を議論するべきである、と考える。
そのことによって、六ケ所村の位置する青森県を「日米原子力共同体」から解き放ったうえで、健全に理性的に原子力発電をどのようにしていくかを議論するべき時に来ている、ということを強く主張する。六ケ所村は、沖縄の名護市辺野古が普天間移設先として背負った十字架と同じ負担を背負わされている。これは「受益地」と「受苦地」の分離という形での官僚やアメリカの大きな国民分断工作なのだ。使用済み核燃料は各原発敷地かそれ以外の電力受益地で保管するべきものだ。原子力発電所問題は、基地問題と似た構図を持つ。
その大きな政策転換のためには、中曽根康弘の流れにある外務官僚が支配してきた、六ケ所村の再処理施設を運営する日本原燃(にほんげんねん)の親会社である日本原電(にほんげんでん)という国策の原子力発電所と核燃料サイクルを主要な事業にする会社を、いちど一時国有化して破綻させ、その上で解体しなければならない。
結局、アメリカの原子力版のジャパン・ハンドラーズとその受け皿である外務省原子力課出身の中曽根系の原子力官僚たちが一番悪いのだ。正力松太郎よりも中曽根康弘が悪いのだ。さらにその先にいる安倍晋三のような日本民族派のふりをしているが、結局はアメリカに逆らえない政治家たちも同様だ。
彼らを日本から一掃して、新しい発想を持った政治家、官僚、財界人、そして国民の議論を活発にさせることによって、日本の原子力政策を正常化させた上で、今後の原子力活用の程度をどのようにするか、という、総合的なエネルギー政策に議論を行わなければならないのである。
この大きな「覇権国-属国」関係を利用する外務官僚の権力の源泉の一つである、六ケ所村の再処理工場を無視、温存したまま、脱原発の議論をやっても、結局はこれらの「原子力外務官僚」の利権を拡大させていくだけである。これが本稿の結論である。
<原発問題は放射能の危険・安全問題ではない>
ただ、その本論を展開していく前に、一般的に認識されている、「原子力発電所は放射能をまき散らすから危険である」とか「原発事故で撒き散らされた放射能は安全なレベルだからすぐにでも原発を再稼働すべきだ」という議論について、考えなければならない。安全とか、危険という言葉で日本人全体がヒステリーになり、専門家でもない一般人が「安全・危険」論争を行うことに意味があるのか。
これは「オスプレイは危険だから飛ばすべきではない」という議論と同じである。その「オスプレイは危険だ」という議論を配備反対派がすれば、とたんに推進派から「オスプレイだけが危険なのではない、他の軍用ヘリも事故を起こしている」という反論が用意されたかのように飛んでくる。そうではなくて根本的な問題はオスプレイが事故を起こした時に、日本政府がアメリカの事故調査に口出しが出来ないという、日米地位協定という不平等条約にある。「安全・危険論」は結局は、水掛け論になる。これは、原子力発電所の事故から放出された放射性物質がどの程度危険なのかを議論する場合でも同じである。
この原発から放出された放射性物質を巡る議論は、結局、「本当に正確な情報が誰にでも検証可能な形で公表されているか」という問題である。その正確な情報が存在していなければ、やはり情報を握っている側は批判されてしかるべきだし、その情報が恣意的に操作されているとするならば、検証した上で、出来る限り操作されていない情報を求めていくべきだろう。その「正しいと大多数が認める情報」を理解したうえで、一般国民が主体的に安全か危険かの判断を自主的に行えばいい。明らかに他のすべてのリスクを負ってでもその場から立ち去ったほうがいいという危険がない場合、必要な情報を入手できる環境を作った上で、政府ではなく個人が選択をする自由が認められるべきである。
この点について、宇井純(ういじゅん)とならぶかたちで、水俣病の健康被害を長年研究してきた、環境リスク学の専門家の中西準子(なかにしじゅんこ)は、福島原発事故後に出版した『リスクと向き合う』(中央公論新社)の中で、リスクとリスクがぶつかった時にどのような合理的選択を一般人が行えばいいのか、という議論の中で、まず次のように述べている。
(引用開始)
ただ、放射線が特別なリスクであると考えるのは間違っています。それによって、何が起きるかはほぼわかっているのですから。低線量の影響がはっきりしない、放射線の影響がわからないからというようなコメントを出す識者も多いですが、それも違います。ここまで影響がわかっているものは少ないのです。原爆が投下され、被ばく者の追跡調査が65年続いているのです。他の物質でこれだけのデータがあるはずがありません。また、国連科学委員会や国際放射線防護委員会(ICRP)を支えた研究者の努力で、ベクレルという放射線の活性をシーベルトという健康影響に換算していくプロセスなどについては、臓器ごとに影響を調べていて、とても化学物質ではできていないことをしているのです。こういうことを知ってもらって、数字通りのリスクだということを理解して欲しいのです。識者の方は、過剰に怖がらせるような発言はゆめゆめ慎んでほしいです。
『リスクと向き合う』中西準子・著(32ページ)
(引用終わり)
このように中西準子は述べたうえで、個々人のリスクの向き合い方について、ICRPが決めた、一人が年間に浴びても良い許容線量限度の1ミリシーベルトという数値について、次のように述べている。
(引用開始)
これ(注:ICRPの許容線量限度)は、どうやってきまったのでしょうか?それはまさに社会が決めたことなのです。自然起源の放射線強度は、ラドンの影響を除くと年1ミリシーベルト程度です。さらに、自然界の放射線が場所によってどのくらい違うかをいろいろ調査した結果、場所による変動も年1ミリシーベルトぐらいでした。場所により高い低いはあるが、そのことは健康に影響を与えていない。放射線濃度の高低によって土地が安いとか高いとか、病気が多いとか、そういうこともない。これなら受け入れられるでしょうね、ということから、年1ミリシーベルトを一応の基準として提案し、多くの国や国際機関がそれを採用しているのです。だからこれは安全基準でも何でもないのです。ただ社会的にそのくらいを標準にして決めましょうという取り決めでしかないのです。
『リスクと向き合う』(34ページ)
(引用終わり)
このように、中西は放射線の許容限度は社会が決めたことであるとし、安全基準ではないとしている。中西は、「リスクはゼロでなければダメだといってしまったら、世の中動かないので、どのくらいのリスクなら受け入れられるかという議論を真正面からしなければならない」、と更に述べている。放射能避難や通常よりも放射能の濃度が高い汚染地域での農業を再開するべきかという問題についても、このリスクを避けることで、他のリスクが生まれる可能性を考えて比較衡量したうえで、個人が判断する自由を政府が与えるべきであるとしている。私もこの考えかたでいいと思う。
ある行動を行った際に、どのようなリスクを個人が負うのかということを考えていくのが政策の判断だということでもある。そのリスクが恐ろしく大きい場合は、その行動をしないままでやめておくということも合理的選択である、ということだ。
以上のような議論を中西の本で読んでいた時、国会内で日本維新の会の西田譲(にしだゆずる)という政治家が「放射能避難」について安倍政権に対して次のような質問をしたことが新聞報道などで話題になっていた。今述べた、中西準子の「リスク・トレードオフ論」からすると非常に奇異な議論に聞こえた。その質問を報じた「朝日新聞」の記事を引用する。
(引用開始)
「低線量セシウムは人体に無害」 維新・西田議員が質問
「朝日新聞」(2013年3月13日・電子版)
日本維新の会の西田譲衆院議員は13日の衆院予算委員会で、福島第一原発事故の放射能汚染について「低線量セシウムは人体に無害。医学を無視し、科学を否定する野蛮な『セシウム強制避難』を全面解除すべきだ」などと質問した。
西田氏の質問に対し、党所属議員の事務所などに抗議があったため、小沢鋭仁国会対策委員長らが対応を協議した。党執行部は西田氏の質問内容を詳細に把握していなかったという。
西田氏は原発事故で飛散したセシウムは「線量は微量だ。個人の外部被曝(ひばく)線量は年間実績でわずか数ミリシーベルト。しかし、これまで進められてきた政策を振り返ると、あたかも日本経済の発展を阻害すべく、反原発を宣伝する手段として、反医学的な福島セシウム避難を考案し、実行したように思われる」とし、被曝の影響は「問題にならない」と主張。安倍晋三首相に避難者の即時帰宅を認めるよう求めた。
除染についても「セシウムしかない福島県でなぜ除染が必要だと考えるのか。住民を排除して民間業者に委託する。何らかの政治的意図から採用したとんでもないやり方だ」と持論を展開。民間業者による農地の除染について「田畑を破壊する。農作物、特に稲にとってセシウムの被害はほとんど考慮に入れる必要はない」と問題点を指摘した。
そして、「原爆の廃虚となった広島と長崎で、放射能で汚染されたがれきを片付けたのは民間業者だったか。生き残った住民が強い意志で日夜営々と努力をしたからこそ、迅速な復興が出来た。福島復興を遅らせている民間業者による除染こそ、即時中断すべきだ」と首相に迫った。
安倍首相は「福島の方に理解を頂ける形で、出来る限り多くの方々が地元に戻れるよう努力したい」などと答えるにとどめた。
橋下徹共同代表は13日夕、西田氏の質問について「個人の意見として述べたんでしょう。表現方法に未熟さがあった」と話した。
http://digital.asahi.com/articles/TKY201303130479.html
(引用終わり)
この西田議員の質問だが後半の除染を民間業者に委託したことの批判はなかなか鋭いし、ゼネコン・土建屋に任せっきりの助成事業を批判したものとして評価できるものだろう。しかし、前半の「医学を無視し、科学を否定する野蛮な『セシウム強制避難』を全面解除すべきだ」は意味が全くわからない。
そもそも原発周辺の住民を菅政権、野田政権、安倍政権が避難させているのは、医学と科学を無視したからではなく、その周辺地域にいずれ、巨大な使用済み核燃料や、低レベル放射性廃棄物の中間保管施設を作ろうとしているからである。また、仮に住民を帰還させても、原子力に依存してきた、福島県の浜通り地方で新しい産業が生まれない限り、放射能の健康被害などの議論を無視しても、住民の生活基盤が確立できる話ではない。住民の側も帰還してしまったら、今もらっている補償金をもらえなくなるリスクがあるので、中西のリスク・トレードオフ論から行けば、全く合理的な選択にはならない。
西田譲議員は国会質問で医学者の高田純などの「WILL」という雑誌によく登場する特定の右翼的な政治思想を持つ論客の言論をそのまま紹介していたようだ。だから、国会議員に必要な生活基盤をどのように作っていくかという議論を大きく無視した的外れな質問になってしまったのだろう。
チェルノブイリの原発事故の結果、ヨウ素被曝の結果、甲状腺がんが増加したことは確認されているから、数年後にかけてこの現象が日本でも起きる可能性はある。また、それ以外の健康被害が起きた場合も、速やかに公表されるべきだろう。その上で、起きてしまった健康被害や健康被害を早期に察知するために、福島県では医療費を無料にするなどの政策は必要なのだろうと思う。
ここまでに紹介した、中西準子の一連の放射能についての議論は、情報を公開した上で、個人がリスク(健康だけではなく金銭的リスク)を勘案して、生活を考えていくべきであることを示しているし、西田議員の質問は、巨大なゼネコンが主導する除染事業の問題を指摘したは思うのだが、私には本当の問題が「その先」にあるという思いの方が強い。それは何かというと、西田議員が指摘した、除染ゼネコン利権を握った環境省の利権よりもさらに大きな「外務省原子力官僚」の存在である。
結局のところ、原発放射能の問題をことさらに議論させていったことに大きな官僚機構の謀略があったのだ。彼らは、官邸前デモに集まる「放射能危険派」をもうまく操って日本の原子力政策を自分達の権益を守る方向に動いた。その証拠が国土交通省でも、経済産業省でもなく、環境省が新しく握った「除染利権」の誕生である。
放射能危険派と安全派がふた手に分かれて不毛な議論を繰り返すことによって、時間が空費されてきた。私が『放射能のタブー』(KKベストセラーズ)で指摘したとおりになった。
しかし、この不毛な議論を繰り広げることで、本当に利益を得るのは「原子力村」と呼ばれるようになった世界に住み、エネルギー政策を牛耳ってきた官僚やその仕組みに乗っかる政治家たちだ。その姿は、冷戦期の保守と革新の議論の「弁証法」の上に立って、日米安全保障体制の護持という権益を脈々と築いてきた外務官僚たちや親米派政治家たちの姿に重なる。賛成派も反対派も彼らの手の上で踊らされてきただけだ。首相官邸前に集まる反原発デモはその矛先を外務省とアメリカ大使館にも、向けるべきであった。
そのような上からコントロールしている、原子力官僚の日本国内での頂点にあるのが「外務省・総合外交政策局・科学原子力課」(現在は、「外務省軍縮不拡散・科学部 不拡散・科学原子力課 国際原子力協力室」と「日米安全保障課」)なのである。本稿は彼ら原子力外務官僚の正体を暴くことを目的にしている。
<「日本はアメリカの核燃料備蓄場」であると喝破した苫米地英人>
このように、日本の原子力政策が「異常」であることはそもそも、日本の原発政策はかつての占領国であり、現在は非対称な同盟関係を結んでいる覇権国のアメリカの許認可によってようやく成り立ってきた、という歴史的な事実に起因している。
そして、その最たる存在は「日米地位協定」であることは前回にお知らせしたとおりだが、この地位協定に基づいた日米安保体制、日米同盟体制を維持したままでは、いかに原子力政策を正常化させようとしても、さらに日米同盟態勢を既得権益にしている日本の外務官僚たちと、アメリカのジャパン・ハンドラーズの思惑に絡め取られてしまうだけなのだ。
そのことを痛感させてくれたのが、苫米地英人(とまべちひでと)が書いた『原発洗脳』(日本文芸社)という本だ。この本の編集者は、偶然にも拙著『ジャパン・ハンドラーズ』の編集をしてくれた編集者であり、そのためか、この本の中でも「ジャパン・ハンドラー」という名称が普通に出てくる。
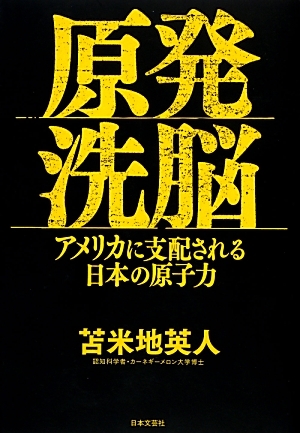
苫米地氏は、1959年生まれの脳認知科学者であり、「自己啓発」(セルフ・ヘルプ)分野の本を多数出している。2012年の衆院選挙では北海道から鈴木宗男の新党大地の候補者としても出馬した。
「苫米地」というと、衆議院の解散により衆議院議員の職を失っために、任期満了までの職の確認と歳費の支給を訴えて争った苫米地事件の主役である苫米地義三(とまべちぎぞう)のことが思い浮かぶが、苫米地英人はこれとは関係ない。
祖父は北海道選出の参議院議員の苫米地英俊であり、父親は日本興業銀行のニューヨーク支店勤務で中学生からアメリカで過ごしている。叔父が米国三菱商事の社長で、米国三菱の公邸のようなところに住んでいたと、自伝(『脳の履歴書』主婦の友社)で書いているから、かなり上の上流階級の御曹司だったのだろう。
上智大学に入学すると、同時通訳を初めてサイマル・インターナショナルで働いてもいる。自分でコネ入社と認めているが、大学卒業後は三菱地所に入社し、社長の通訳を務めていたので、ロックフェラーセンター買収にも関わっており、デイヴィッド・ロックフェラーとも個人的に親しく、ロックフェラー・グループの取締役会には常に三菱地所の苫米地氏の座席があったほどだという。
フルブライト留学生でもありイエール大学で人工知能について学んだ後、カーネギーメロン大学に転入し、日本人としては初の博士号を取った。
その後、日本では、徳島大学や「一太郎」で有名なジャストシステムで勤務していたが、オウム真理教事件があった後は、その元オウム信者の脱洗脳に関わったことで有名になった。CIAの洗脳プログラムについての訳書もある。洗脳をキーワードにし文筆・評論活動を続けている人である。
苫米地氏は金融危機の直前くらいから、マスコミの洗脳などによって一般人が見落としている世界の秘密を暴くべきだ、と主張する本を書くようになった。だから、今回の『原発洗脳』という本も、日本人の脳に生まれた「盲点」(スコトーマ)を暴くという狙いで書かれたものである。
そしてその彼の言う「盲点」とは、「日本の原子力は米国に支配されている」ということである。だから、この本は「原子力版の属国・日本論」ともいうべき本なのだ。
だから、私としては苫米地氏の本を読んだ上で、それを踏まえて、実際に具体的に日米の原子力共同体はどのような人物たちで構成されており、誰が一番重要なキーパーソンなのかを暴き立てなければならない、ということになる。
苫米地氏は、この本の中で「日本の原子力を今もアメリカが支配している」という重要な事実について述べている。
具体的にはそれはどういうことかというと、「日本の原子力の技術はアメリカではもはや古臭いものになった民生技術であり、本当に優れた高度なアメリカの原子力技術はウェスティングハウスの原子炉を備えた米原子力空母の軍事技術である」ということなのだ。
『原発洗脳』から引用しよう。「原子力技術に関しては、日本は最高レベルだという意見」に対して、「何を根拠にそのようなことを言っているのか、全く理解出来ません」と述べて、苫米地氏は、次のように書いている。
(引用開始)
確かに、日立、東芝、三菱は、世界の原子力の主要プレイヤーであり、東芝は高い原発技術を持つアメリカのウェスティングハウス・エレクトリックの原子力部門を傘下に収めています。
しかし、ウェスティングハウスは東芝の傘下には入りましたが、核分裂を持つコアの技術は手放していません。がっちりと握ったままです。依然として中核技術の特許は押さえています。(略)
ウェスティングハウスは、軍事機密の部門を切り離して、残りを東芝のコントロール下に置いたのです。東芝が買った技術は、原子力発電のいわば「メンテナンス技術」だけです。原子力発電のコアの部分である核分裂技術に関しては、何ら技術を持っていません。
『原発洗脳』(六九-七〇ページ)
(引用終わり)
このように述べており、戦闘機の分野と同じように、日本は属国なので、中核技術は決してブラックボックスのままにされて、アメリカから譲り渡してもらえないのだ、と述べている。さらに、次に、GEの沸騰水型原子炉に関しても苫米地氏は次のように述べている。これは、私が実際に原発メーカーの技術者から聞いたのと同じようなことだ。
(引用開始)
原発建設に関わった技術者を知っていますが、実際の現場では、GE(ゼネラル・エレクトリック)などの特許をマニュアル化した知的財産権のルールが細かく規定されていて、その範囲内で、マニュアル通りに技術者が動いているだけです。
福島第一原発1号機は、GEが主契約者で、2号機はGEと東芝が主契約者でした。3号機と4号機は、東芝と日立が主契約者でしたが、東電からの元請けが東芝と日立というだけであって、GEの技術者が来て、その指示のもとに作ったのです。(略)このような実態がある中で、「日本が世界最高の原発技術を持っている」とは、とても言えないはずです。(略)
言い方は酷になりますが、東芝と日立は、アメリカの原子力技術の販売代理店に過ぎません。日本企業がベトナムやトルコに原発を売れば、特許収入がアメリカに転がり込む仕組みなのです。日本の原発施設は、アメリカ企業にとって、住宅展示場のようなものです。
『原発洗脳』(72-73ページ)
(引用終わり)
このように苫米地氏は見抜いている。確かに、アメリカでは今日まで30年間、スリーマイル島のメルタダウン事故以降、アメリカ国内では原発アレルギーが起こり、その一方でロックフェラー系のカーター政権などは石油戦略を打ち出したので原子力がスローダウンしたので原発の視線説はなされなかった。
アメリカでは民主党のカーター政権でスリーマイル事故が起きたあとに、使用済み核燃料の再処理を含めた原子力民生ビジネスに対して意欲を失っていく。その間にも、日本は田中角栄の「電源三法」に代表されるような、地方への原発誘致と引き換えに莫大な補助金を流してこんで、地方を電力需要の必要上にたくさんの「原発銀座」にしてしまった。
これが苫米地氏の言うとおりであるならば、これはアメリカが属国から「金を巻き上げるビジネス」の一貫として機能していた、ということにほかならない。
後でも述べるが、原子力ビジネスというものはそもそもアメリカと日本が原子力協定を結んだからこそ、実施が許されたものであり、アメリカは許認可、ライセンスを与える立場になるのである。田中角栄の後にもアメリカのお気に入りの中曽根政権になっても原発建設が止まらなかったことは理解できる。
ところで、本当に優れた原子力技術とは何か、についても苫米地氏は語っている。それは、ウェスティングハウスの技術を駆使して作られたアメリカの原子力空母「ロナルド・レーガン」に2基搭載されたA4W原子炉であるのだという。この空母は311直後のトモダチ作戦に参加した空母だ。
ちなみに原子力空母を建造しているのはノースロップ・グラマンで、その原子炉の設計はウェスティングハウスであるが、原子力潜水艦の場合はクラスによって同じPWR(加圧水型原子炉)であっても、GEとウェスティングハウスの両方のタイプがある。原子力潜水艦にもGEは参加しており、商業軽水炉では保有していないPWRを持っているのだ。これは私が苫米地氏の本を読んだ後に調べてわかったことである。潜水艦本体を建造しているのは、リチャード・アーミテージがかつて取締役をしていたゼネラル・ダイナミクス社だ。
さて、この原子力空母の原子炉が優れているのかということについて、苫米地氏は次のように語っている。
(引用開始)
空母に搭載している原子炉は、出力調整が可能な原子炉です。スロットルのように、「15パーセント臨界」、「50パーセント臨界」などの調整が可能で、必要な電力量に応じて、出力を自由に変えられるのです。商業用原子炉とは、比較にならないほど、高度なテクノロジーが使われています。
『原発洗脳』(105ページ)
(引用終わり)
これを読んで、改めて私はいかに、商業用原子炉の技術が遅れているものなのかわかったような気がした。アメリカは民生用に売り渡してもいい技術だけを選んで売って、軍事技術は最先端を維持していく。おそらくDARPAのような軍事通信技術を研究しているところも、そのようにしてインターネットを民間に売り渡したはずで、軍事ではもっと高度な通信技術が使われているのだろう。
いずれにせよ、今一番多いとされる日本の原発は、1970年代に開発された第二世代の原子力技術で作られたものであり、つまりそれは30年前の遅れた技術によるものである。しかも、その古い技術で建設された原子炉を新幹線のような他のインフラの入れ替えのペースでは考えられない30年以上とか、場合によってはアメリカでは60年近くも使い続けるということなのだ。40年経てば、トンネルも崩れる。同じように原発も壊れる。それが福島第一原発の事故だったということだ。それでも、福島の事故は、非常用の送電線やディーゼル発電機をを複数確保すると対応が可能だった。それをコストをけちって東電がやらなかったし、規制当局もそれを容認した、ということが事故の背景にある。連鎖的な原子炉のメルトダウンは本来起きなくてもいい事故だったのだ。
話を戻すと、もともと原子力技術というのはウェスティングハウスの原子炉を搭載したノーチラス号(建造はゼネラル・ダイナミクス社)という原子力潜水艦から始まったものであり、もともと原子炉は巨大なものではなく小型なものだった。また、原発で使うような数パーセントの低濃度濃縮ウランではなく、原爆以上の95パーセントの高濃度濃縮ウランを使うものだという。小型で燃料は、潜水艦が退役するまでの40年~50年まで一度も交換しないで済むという「使い捨て型」なのだ。
そこで思い当たるのが、アメリカではすでに、ビル・ゲイツなどが絡んだ形で、小型原子炉の開発が進められているということである。ゲイツが出資する「テラ・パワー」には民間の原子力発電の未来があり、小型・使い捨て(30年間燃料交換不要)というのがそのキーワードである。これもおそらくは軍事技術の転用なのだろう。東芝もすでに小型原子炉「4S」を作っているが、やはりウェスティングハウスの技術の転用と見るべきだろう。テラ・パワーは、「ウラン濃縮施設の無用化、最終的には廃止」と「将来的な再処理工場の無用化」を会社の目標に掲げている。だから、今日本で議論されている核燃料サイクルなどの議論はすごく遅れた話なのだ。このことについては後で本格的に触れる。
苫米地英人の『原発洗脳』に話を戻す。このように、苫米地氏は日本の原子力技術がアメリカの最新の軍用の原子力技術に比べても、民間の最新の原子力技術に比べても大きく遅れていることを述べた上で、本書の本当に重要な「アメリカの日本に原子力支配」について論じている。
ここで、アメリカの許可なしに日本が原子力を持つ事ができた、と考える人は、日本がアメリカと戦争で殺し合ったという事実を無視しているのと同じだとのている。アメリカの敵国であった日本がすんなりと戦後わずか10年後(1955年)に原子力を持つことが出来たのは、アメリカの国益が背後にあったためだと述べているが、苫米地氏が優れているのは、彼が次のように述べているところである。
(引用開始)
アメリカにとっての国益とは、「安全保障(ナショナル・セキュリティ)」です。日本の原発は、アメリカの安全保障を脅かさず、アメリカの安全保障に寄与することを条件に認められた私設です。この条件なしには、アメリカは日本に原発を認めることはありませんでした。つまり、原発は、アメリカの管轄下に置かれ、アメリカがコントロールすることを前提にして、敵国・日本に認めた施設なのです。この条件を担保するもののが、日米安全保障条約です。こういった経緯を踏まえずして、原発問題を議論してもほとんど意味がありません。
『原発洗脳』(117ページ)
(引用終わり)
このことが極めて重要である。属国・日本論の立場と合理的選択論で政治分析をする立場からすれば、苫米地氏の上の文章は次のように言い換えられるだろう。
○ アメリカは、日本に商業用原子力発電をやらせるという「合理的選択」を行なっている。
アメリカが敵国・日本に、商業用原子力発電を認めるための論法の一つが、アイゼンハワー大統領が核保有国アメリカの大統領として打ち出した、「アトムズ・フォー・ピース」(平和のための原子力)というプロパガンダである。原子力発電というのは先程も原子力空母や潜水艦の例を引き合いに出して述べたように、元々は核爆弾や原子力推力の潜水艦からの「スピンオフ技術」に過ぎない。
核戦争の脅威を前提にした「米ソ冷戦」が激化する中、アメリカは敵国であった日本を反ソ陣営に繋ぎ止めておくために、日本には核兵器開発をさせずに原子力発電だけを与える。これが戦後一貫したアメリカの国家戦略の合理性であった。そのためには、アメリカは日本の原子力施設を徹底的に監視するし、それに対して、日本の政治家はそれを出しぬいて、少しでも自力核武装をする可能性を残そうとする。
したがって、これは合理的選択論で見るところの、「プリンシパル(本人)-エージェント(代理人)関係」そのものであり、アメリカの監視の目を盗んで核武装につながるプルトニウムを貯めこむことは、エージェンシー・スラックを利用した代理人の側の反逆行為であるということになる。
エージェントが、プリンシパルの利益のために委任されているにもかかわらず、プリンシパルの利益に反してエージェント自身の利益を優先した行動をとってしまうことを、エージェンシー問題という。
そこで重要になるのはプリンシパルがこの死活的な安全保障上の利益をめぐってエージェンシー問題(この場合には日本の「独自核武装」と「日米安保条約の破棄」)を回避するための日本コントロール方法を構築するように、当然、プリンシパルである覇権国・アメリカが賢ければ手をうってくる。
それが「人脈(ネットワーク)」を通じたエージェント側のコントロールである。ただし、現在はアメリカは日本が「核武装ではなく、潜在的な核武装につながる技術を持つという、核技術抑止論を公然と打ち出す」ところまでは、監視つきで認めているようである。そのような核技術による抑止論を捨てない、と公言する石破茂・自民党幹事長に代表される政治家がアメリカに抹殺されないことがその証拠である。
しかし、それができるのも、プリンシパルであるアメリカは、日本の原子力施設を常に監視しているからである。アメリカは日本の発電所の運転状況、原子炉に搭載された燃料の一本、一本まで日本から報告を受ける権利がある。
そのようなことを可能にしているのが「日米原子力協定」である。(報告についての規定は、実際には協定の実施取極第2条に規定される)
苫米地氏は細かくは日米原子力協定については述べていない。しかし、本質的に苫米地氏は米日の覇権国・属国関係と、それが意味することを概念として理解した上で、この本を書いていることがわかる。そのことを示しているのが以下の文章である。『原発洗脳』から引用する。
(引用開始)
アメリカの安全保障政策上、日本は、アメリカの「核の傘」の下に置かれた国です。日米安全保障条約によって、他国が日本を攻撃したら、アメリカの核による報復攻撃が行われることになっています。そのかわりに、日本は確の置き場所という位置づけも持たされています。アメリカ軍の核兵器が不足した場合には、日本の原発の核燃料などを接収して、アメリカ軍の核兵器などに転用します。日本の原発はアメリカの核燃料備蓄場といってもいいくらいです。
日本が、核燃料サイクルで燃料の再処理をして、プルトニウムなどを保有することが求められているのも、アメリカがいつでも接収できることが前提になっています。
『原発洗脳』(125ページ)
(引用終わり)
ここには驚くべき日米関係の真実が書かれている。
<日米原子力協定を分析しなければ日本の原子力政策の異常さは理解できない>
苫米地氏が書いている、プルトニウムを「接収」というのは、極端なように聞こえる話だが、究極的には本当なのだ。
なぜなら、そのように日米原子力協定では明瞭に書かれているのだ。日米地位協定で、アメリカが日本のどこにでも基地をおいても許されるし、米軍の飛行機やヘリがどこを訓練しても許されるようになっているから、日本側がオスプレイの飛行を拒否できないのと、理屈は同じだ。アメリカは協定や契約に書かれていないことはやらない。書かれていることに基づいて、行動する。
実際に日本にあるプルトニウムが接収されていないのは、アメリカが実際にその必要性を感じていないから、それをやらないだけだ。
だが、日米原子力協定には安全保障条項というものがある。そこに接収のこともちゃんと書いてあるのだ。
今述べた、この日米原子力協定とは、1988年に発効した現行協定のことをいう。後で述べるが、原子力協定には1955年版の「日米原子力研究協定」それから1968年版の「旧日米原子力協定」がある。
正式名称は、「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」という。序文では、「1968年2月26日に署名された原子力の非軍事的利用に関する協定のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(その改正を含む。)(以下「旧協定」という。)の下での原子力の平和的利用における両国間の緊密な協力を考慮する」と述べてある。
つまり、旧協定の効力をも引き継いでいるものだ。旧協定よりも現行協定は、かなり記載が簡略化されている。つまり現協定と矛盾しない限り、旧協定も合わせて適用される、ということである。
そして、この原子力協定第11条には次のように書いてある。
(引用開始)
第11条
第3条、第4条又は第5条の規定の適用を受ける活動を容易にするため、両当事国政府は、これらの条に定める合意の要件を、長期性、予見可能性及び信頼性のある基礎の上に、かつ、それぞれの国における原子力の平和的利用を一層容易にする態様で満たす別個の取極を、核拡散の防止の目的及びそれぞれの国家安全保障の利益に合致するよう締結し、かつ、誠実に履行する。
(引用終わり)
この中で書かれているのは、第3条(ウランや濃縮ウラン等の貯蔵について)、第4条(核物質や資材の日米間の移転について)、第5条(使用済み核燃料やプルトニウムの再処理の権限を日本に認める件について)の各規定の適用を受ける活動をしやすくするために、日米両政府は、「長期性、予見可能性及び信頼性のある基礎の上に、かつ、それぞれの国における原子力の平和的利用を一層容易にする態様で満たす別個の取り決め」を締結するということだ。
さらに、それは核不拡散体制(NPT体制)や、日米の(つまりアメリカの)安全保障上の利益に合致するように締結され、日本は誠実にそれを履行する義務があるということである。
形式上、双務的に協定上の義務は及ぶことになっているが、日本がアメリカに命令できることは、日米安全保障条約や地位協定の規定を考えればありえないので、これは事実上、日本だけに課される義務である。
そして、この11条で書かれている取り決めというのが、「協定第11条に基づく両国政府の間の実施取極」である。日米地位協定に対する交換公文のような位置づけにある文書である。その中には次のような安全保障条項を更に具体化させる記述が書かれているのだ。ちょっと長いが、これまで解説してきたことを踏まえた上で読んでいただければ十分に理解できる内容だと思う。
(引用開始)
第3条
1(略)
2 いずれの一方の当事国政府も、他方の当事国政府による核兵器の不拡散に関 する条約に対する重大な違反若しくは同条約からの脱退又は機関との保障措置 協定、この実施取極若しくは協力協定に対する重大な違反のような例外的事件 に起因する核拡散の危険又は自国の国家安全保障に対する脅威の著しい増大を 防止するため、第1条において与える同意の全部又は一部を停止することができる。そのような停止に関する決定は、核不拡散又は国家安全保障の見地から の例外的に懸念すべき最も極端な状況下に限り、かつ、政府の最高レベルにお いて行われるものとし、また、両当事国政府が受け入れることのできる態様で そのような例外的事件を処理するために必要とされる最小限の範囲及び最小限の期間に限つて適用される。
3 両当事国政府は、2の停止の期間中、第1条に掲げる活動について個別に合意することができる。両当事国政府は、問題とされる事実関係を確定するため に、及び停止が必要な場合にはいかなる範囲の停止が必要であるかを討議する ために、停止に先立ち相互に協議する。停止を行う当事国政府は、当該停止の経済的影響を慎重に検討し、かつ、この実施取極の下での国際的な原子力関係取引及び燃料サイクルの運営の撹(かく)乱を回避するため可能な最大限の努力をする。 両当事国政府は、協力協定第14条の規定に従い、これらの問題を解決するた め第三者に付託することを合意することができる。
4 停止を行つた当事国政府は、停止の原因となつた事態の進展を絶えず再検討 し、かつ、正当化され次第停止を撤回する。両当事国政府は、いずれか一方の 当事国政府の要請があつた場合には直ちに、当該停止の撤回のための根拠の存 否を決定するため相互に協議する。
「日米原子力協定第11条に基づく両国政府の間の実施取極」
(引用終わり)
この取極第3条が作られた理由は、当時、外務省で日米原子力協定の交渉に携わった、遠藤哲也という官僚が自ら記した回想録『日米原子力協定(1988年)の成立経緯と今後の問題点』に詳しく書いてある。
遠藤らによると、1988年の日米原子力協定の改定交渉の力点は、これまでの協定ではアメリカが日本に一回ごとの個別同意を与えることでなんとか許容されていた、使用済み核燃料の再処理について、アメリカが包括的な合意を与えることをアメリカに容認させるというところにあった。
この背景には核兵器生産につながるプルトニウム生産のフリーハンドを得ておきたいという国家戦略的な日本の思惑と同時に、電力会社側の副社長クラスが毎回、米議会の校長会に呼び出されるという手間を省くという目的もあったようだ。実際、日本初の再処理施設である東海村再処理工場は運転開始直前に、米国が稼働を停止させたこともあった。(この件は『原発の闇』赤旗編集局などに記述がある)
原発から出る「使用済み核燃料」を再処理して、再び核燃料(MOX燃料)にするプロセスを「核燃料サイクル」と呼ぶ。その際には、核兵器のそのまま原料になる危険なプルトニウムという物質が分離される。アメリカはこの再処理を他の国には与えていなかったが、この改定協定を結んで、日本に与えることにした。
ところが、それは無条件ではなく、協定本文と実施取極に「国家安全保障」というアメリカの国家意思を表す表現を入れることが条件だった。それを交渉にあたった外務官僚やその当時の首相だった中曽根康弘に呑ませたのである。
そして、それが実施取極め第3条第2項にある「全部または一部の停止」という条項なのである。属国が勝手に核武装をしてアメリカの核の傘から離れることをアメリカは阻止するためにこの条項を日本側に飲ませたのだ。
日本は今も原発で使用する濃縮ウランの7割以上をアメリカから購入している。もちろん、ウラン鉱石の最大の輸入元はアメリカではない。オーストラリアであり、二番目はカナダである。しかし、これが原発で使われる濃縮ウランになると、アメリカが筆頭に来る。この根拠となっているのが、どうやら、68年の原子力協定に取極めがあるらしい。
実際の輸入量の総計は、2004年から2010年の合計では、今もアメリカからが73%(4602.7トン)、ついでフランス(1146.2トン)となっている。日本国内にもウラン濃縮工場はあるが生産しているのは、全体からすれば、じつに微々たる量である。
また、原子力委員会が出した『昭和62年版原子力白書』は、日本の発電事業者が米国以外からの濃縮ウランを混焼(混ぜて燃やす)する場合、米国以外の濃縮ウランの割合を30%を上限にする契約を結んでいると書いているという。当初は100%近い量を米国から輸入してきたことを考えれば、濃縮ウランの供給源は多様化されたと言えるが、まだまだである。(前出『原発の闇』から)
そのように原子力協定というのはよく読めば、日本の原子力事業というのがアメリカからの許認可を前提にしたものだとわかってくる。話を苫米地英人氏の『原発洗脳』に再び戻す。
苫米地氏は、日本の原発にアメリカは備蓄しているのだと書く。イランのようなイスラエルの敵国が、核兵器開発するために原子力発電所を動かそうとしていることを考えれば、この理屈は容易に理解されるだろう。
原発というものの前に原子爆弾があり、原子力潜水艦があった。いざとなれば核兵器製造の原料を取り出せる設備が原子力発電所なのだ。さらに、日本には劣化ウラン工場もあり、劣化ウラン弾の製造も日本が肩代わりをしていることになる。劣化ウランの工場は、日本では山口県岩国基地の近く、アメリカではグアムかハワイにあるらしい。
去年、2012年4月22日に、三井化学大竹工場で火災が起きたことがあった。その時もこの工場では劣化ウランを製造しているという報道が流れたことを今思い出した。
この工場には、放射性物質である「劣化ウラン」が入ったドラム缶をおよそ3,400本保管しているとも当時報道された。当然、これらの劣化ウランは直近にある米軍岩国基地に劣化ウラン弾として納入されているのだろう。劣化ウラン弾は戦車の装甲板も貫通する能力を持っており、タングステンと並ぶ兵器の原料であることはよく知られている。ただ、イラク戦争で劣化ウラン弾を使う戦場にいた米軍帰還兵やイラクの人々は後遺症に悩まされていて、このことはアメリカ国内でも映画になったほどの大問題になっている。
アメリカ本土では世論の反対が強く、劣化ウラン弾工場を建設できないので属国でやっている。そのように苫米地氏は書いているがその通りだろう。
だから、苫米地氏は次のように言い切っている。
(引用開始)
原発施設は、表面的には、日本の民間企業の施設ですが、現実にはアメリカ軍の「軍事施設」と言っても過言ではありません。
『原発洗脳』(128ページ)
(引用終わり)
日本の原発はアメリカの核の一時的保管所であり、日本の原発ビジネスはアメリカがコストを負わない代わりに日本の原子炉メーカーがアメリカの下請けとしてライセンスを付与されているだけのビジネスである。
この苫米地氏の鋭い読みを私は高く評価しなければならないと思う。確かに沖縄の嘉手納基地や辺野古のキャンプ・シュワブに米軍が核兵器を持ち込んでそれを保管しているという話は証言としても出てきていた。しかし、それと同じようにアメリカは核兵器ではないが、核物質を移動させて管理していた。それが日米原子力協定に規定された、「核物質や施設、設備の管轄国間の移転」というものである。いずれにせよ、最終的には核物質を装填した日本の原発は緊急時にはアメリカの管轄に行くのである。
東電福島第一原発のメルトダウンに際して米軍が全面協力を申し入れ、更に首相官邸にNRCや大使館の関係者を常駐させたののも、原子力協定第2条に規定された、「両当事国政府は、専門家の交換による両国の公私の組織の間における協力を助長する」とか「両当事国政府は、両当事国政府が適当と認めるその他の方法で協力することができる」というものに基づく、専門家の交換という取極めの実行に過ぎない。
世間で、原子力村と呼ばれる原子力に群がる既得権利権集団の存在が囁かれて久しい。
しかし、これまでの議論ではいわゆる「政官業の鉄のトライアングル」ということにまで注目が行くようになっていたが、実際はそのトライアングルを上から支配するアメリカという存在がある。このことが重要であり、そのことに気が付かなければ、脱原発を巡る議論は「あさっての方向」に行ってしまう。
その最たる例は「発送電分離さえ行えば、脱原発は実現できる」というものであり、これを唱えていたのが、今年になってから亡くなった加藤寛(かとうひろし)・千葉商科大学元学長である。
カトカンは合理的選択論から生まれた、ジェイムズ・ブキャナンという行政学者の「公共選択論」を日本で広めた人である。官僚の肥大化をどうやって防ぐのかということを研究する学問だ。合理的選択論のように価値中立的に、関係者の行動原理を分析して、一方が他方をコントロールするのではなく、もっと倫理的な動機に基づいたものだといっていい。カトカンは絶筆として『日本再生最終勧告:原発即時ゼロで未来を拓く』(ビジネス社)というまさに倫理的な動機に基づいた本を残した。
彼は、官僚を政治家がコントロールするべきだと言うまでのことは言うのだが、やっぱりこの「覇権国-属国」関係が見えていないので、政策提言は「発送電分離止まり」である。本当は、発送電分離が要らないというのではないが、問題の本質はそこではない。苫米地氏は、発送電分離は不要であり、国内改革で必要なのは東西で電力の周波数が違うのでそれを統一すれば十分であり、それにはコストは大して掛からない、としている。
加藤氏も同じようなことを述べているが、力点は発送電分離という送電会社と発電会社の分離に置いている。この発送電分離は竹中平蔵や小泉純一郎も支持している。
だから、こう言わなければならない。私は発送電分離には必ずしも反対はしない。しかし、よほど制度設計に気をつけないと、アメリカや欧州の外資系電力会社や金融会社のエジキになってしまう危険性があることは指摘して置かなければならない。
以上が、苫米地英人の『原発洗脳』という本の内容を踏まえた、私なりの合理的選択論の立場からする理解である。
最後に、「原子力村の住民一覧」という資料サイトが作成したわかりやすい、日米原子力関係の真実を表す図表を掲示しておきたい。これに書かれた大きな枠組みを踏まえて次に、具体的な日米原子力人脈についての研究を、有馬哲夫『原発と原爆』やその他の中曽根系の政治家の回想録を踏まえながら行なって行きたい。
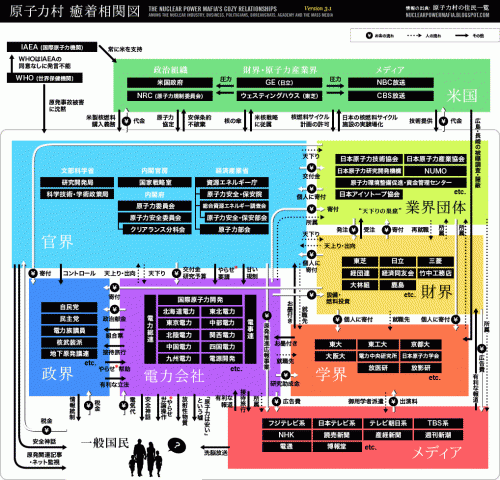
出典:http://nuclearpowermafia.blogspot.jp
とりあえず、一度筆を置く。